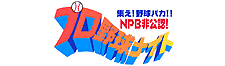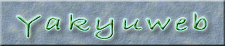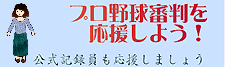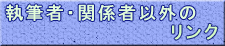プレイボールとゲームセットの間に by 粟村哲志
第31回 「『あそこに投げないと抑えられない』は本当か?」
中日ドラゴンズのタイロン・ウッズ選手が、試合中にヤクルトスワローズの藤井秀悟投手を殴打した事件から1ヶ月が経過したが、その後もセ・パ交流戦の西武−巨人のカードで死球をめぐるトラブルから警告試合が行われるなど、野球の本来の姿からは逸脱した事件が相次いだ。
このような異常事態に対処することも、本意ではないが審判員の役割である。実際にトラブルが起こってしまった際の対処はもちろんのこと、トラブルを未然に防ぐことも大切で、どんな場合でも冷静な対処が求められる。
公認野球規則8.02(d)は、投手が打者を狙って投球することを禁じている。このような反則行為が起きたと判断したら、審判員はその投手または投手と監督を退場にするか、次にそのような行為が行われたら退場処分を下す旨を両チームに警告しなければならないと定められている。この警告は、試合中だけでなく、必要があれば試合開始前になされてもよいとルールは定めており、冒頭で触れた西武−巨人3回戦の「警告試合」とはこれにあたる。
報復の死球合戦が半ば不文律となっているといわれる米国球界ではこのような警告や退場は残念ながら多く行われており、審判学校や、プロ審判への最終テストであるPBUCのトレーニングでも対処の仕方や心構えがきちんと指導されるそうである。
メジャーリーグの審判マニュアルにも、このことは明記されている。
わが国のプロ野球では、このようなケースについては米国ほどひどくはないが、それでも過去にはいくつかのトラブルがあり、いわゆる「危険球」に対するガイドラインも整備された。
しかし、もっと問題だと思うのは、「ぶつけるくらいの気持ちで」あるいは「ぶつけてもかまわないから」内角を厳しく攻めなければ投手は生き残れない、というような風潮がまかり通っていることだと思う。
ウッズ選手の問題にしても、当の藤井選手本人がメディアに対して「あそこに投げないと抑えられないですから。当てることなんてしない。次からだって投げないと」(5/6付サンケイスポーツ)といった内容のコメントをしているが、顔面近くに投げることがはたして野球本来の姿だろうか。プロ野球選手のレベルで、すっぽ抜けと意図的なブラッシュボールは明らかに異なる。過去には頭部に死球を受けて死に至ったり、その後の野球人生を棒に振った選手が何人もいる。
スポーツに励み、不慮の事故で故障するなら仕方がない。しかし、危険を承知の上で硬式球を投げつける蛮行(と本人は思っていないと思うが)は許されるべきことではない。暴力行為に及んだウッズ選手を擁護することはできないが、藤井投手がただ被害者になっている構図は正しいとは思えない。現在のルール解釈では藤井投手を規則で罰することはできないが、何らかの問題意識を皆が持つことが必要だと感じている。
第32回 「むかしばなし」
ごく一時期のことだが、球審を担当しているときに、「キラキラした光る筋」とでもいったものを空気中に見ていたことがある。この話は、なんだか少しオカルトめいているのであまり人にはしないのだが、最近思い出したので書いてみることにする。
リトルシニアで審判を始めて間もないころ、私はひとつの大きな壁にぶつかっていた。それまでは独学で審判法を勉強した「つもり」になっていて、道具を買い込んで草野球の一人審判などを時々していたのだが、組織に所属し、毎週毎週グラウンドに立って試合を裁き続けるようになり、ストライクゾーンというものがさっぱりわからなくなってしまった時期があった。
今から考えれば、きちんとした教育を受けないままに「なんとなく」審判をしていたのだから当然といえば当然なのだが、試合後の反省会で「ストライクゾーンがちょっとおかしいね」「少し低目をとりすぎだ」「高目がぜんぜんとれてない」などの講評を聞くたびに自信を喪失し、泣きそうな気持ちでマスクをかぶっていた時期もある。
それでも、そのときはガムシャラに努力した。機会があればどんな試合の審判でも引き受け、土曜も日曜もなく、時には平日さえもグランドに立ち、チームの練習に参加してブルペンに入らせてもらったり、フリーバッティングのケージの後ろに立ったりして、考えられ得る努力はすべてした。仕事をしながらとはいえ、身分は一応学生だったこともあり、今から考えても野球付けの毎日を送っていたと思う。
そうこうしているうちに、なんとなくストライクゾーンが体に染み付いてきて、ある程度自信を持って投球判定に臨めるようになってきた。もうはっきりとは覚えていないが、1年ほど時間がかかったように記憶している。そんなある日、「あの光」が見えたのである。
投手が投球動作に入り、私が捕手の後ろでセットする。すると、ストライクゾーンの外角いっぱいのあたりに、一筋の光がチラチラしているように感じた。最初は目の錯覚かとも思った。しかし、何度構えても同じところにキラキラと輝く漠然としたものが見えるのである。半信半疑ながら、その光の筋を頼りに外角の判定を行ったところ、これが実に具合がいい。選手からも不満は出ないし、試合後のミーティングでも、ゾーンのことで指摘を受けることがなくなった。
現在一般的になっている「スロットポジション」と呼ばれる球審の構えの基本は、打者の内角寄りに自分の顔をセットして、打者と捕手の間に存在する隙間(スロット)からストライクゾーンの全体を確保する事を絶対条件とするが、この構え方の難しいところは、自分から遠い方になる外角の感覚をつかむことにある。その感覚を、ある一時期、この光の筋が教えてくれたのだと思っている。
以前何かの本で読んだことがあるが、あの江夏豊投手も現役時代には外角に同じような光の筋が見えていたという。往年の大投手と比較するなどおこがましいとは思うが、何かをつかもうと思って努力すれば、だれにでもそういう瞬間が来るのかもしれないと思っている。
ちなみにその光は、今は見えない。その後見えなくなってしまったのである。しかし、いまではことさらに意識しなくとも、自分の身体からの距離感で、外角も低めもよくわかるようになってきた。ひとつには、米国審判学校式の基本技術を教わる機会に恵まれたこともあるかもしれない。それにしても、あの光が見えていたあの時期、私はわれながらよくがんばったと思うし、そのことに対する野球の神様からのご褒美だったのかもしれないと感じている。
第33回 「審判泣かせの『振り逃げ』事件」
シカゴ・ホワイトソックス対ロサンゼルス・エンゼルスのアメリカン・リーグ優勝決定シリーズ第2戦。ホワイトソックスのサヨナラ勝ちにつながったA.J.ピアジンスキーの「振り逃げ」について少し考えてみる。
早くも「世紀の大誤審」などという表現も使われているが、判定自体は難しいもので、誤審と決めつけることは適切でないと私は思う。捕手が投球をワンバウンドでなく正規に捕球したかどうかは、場合によっては球審にとって非常に確認の難しいプレイになることがあり、捕球音や地面とボールが接触する音、また選手の様子なども参考にしながら慎重に判断されなければならい。球審は一番近くにいるのだからしっかり見えるはずだとお思いの方もあるかもしれないが、角度によっては捕球点が全く見えないことも往々にしてあるものだ。
米国マイナーリーグで審判を務めていた藤原啓之さんに以前聞いたところでは、藤原さんはパートナーとこういう場合の秘密のサインを取り決めていたそうで、塁審から見て「球審にとって難しいプレイだ」と感じたら、選手やベンチに知られないようこっそりと「ノーバウンド」「ワンバウンド」を知らせることにしていたという。このサインは投球だけでなく、ファウルチップの場合にも有効である。同様の話は2000年のシドニー五輪に派遣された国際審判員の小山克仁さんからも聞いたことがある。
エンゼルスのジョシュ・ポール捕手は問題の投球を「捕球」した後、ボールをグラウンドに放り出してベンチに帰ろうとしたが、たとえ完全捕球の自信があったにせよ、これはいささか軽率な行動であっただろう。地面スレスレで捕球したような場合は、念のため打者にそのままタッグすれば間違いなくアウトになるのであり、これは球審に対する親切ということにもなる。
ただし、ダグ・エディングス球審の行動にも若干の問題がある。試合後エディングス球審は、「『キャッチしていない』と言っていない。捕手のポールが何をするのかしっかりと見ていた。そうしたらピアジンスキーが一塁へ走り出した」「自分の判断は正しかった。キャッチするときに(ボールが地面に当たったような)2つの音が聞こえた。(ポールは)ダイレクトキャッチしていない」と語っているが、このこと自体は全く正しい主張である。
第3ストライクだけれども、捕手が正規に捕球していないために、まだ打者はアウトでないといった状況のとき、日本では「ストライクスリー」あるいは「スイング」だけを宣告してプレイを続行させるが、米国では一般的に「ノーキャッチ」の宣告もしたり、両手を広げる(セーフと同様の)メカニックも入れてしっかりと球場中に知らせるようにする。
ただし、スイングを示すのに通常のストライクと同じようなゲンコツを握ったメカニックを使うとアウトと紛らわしいので、例えば指を1本立てて高々と上げておくとか、何か「スイングしたけどまだアウトではない」ということがわかりやすいような工夫を各審判員ともしている。
ところが、エディングス球審の動きをビデオで確認すると、ピアジンスキーが空振りしたとき、まず最初にエディングス球審は手刀を切るように右手を真横にすっと伸ばしている。これは彼にとってスイングを表したメカニックである。このままじっとしていたのなら、彼が主張する「何も宣告しないでプレイを見定めていた」とうことで理解できるのだが、エディングス球審は右に伸ばした手を身体の前面に移動させ、軽く握り拳をつくって前方を叩くような仕草を見せた。これがいかにもまずかった。エディングス球審のメカニックは、どう見ても「スイング」→「アウト」と思えてしまう。右手を右に伸ばし、その後で握り拳をつくるところまでワンセットで「スイング」だけを表しているのだと主張しても、いささか説得力に欠ける。
捕手や打者はこういった場合、球審のそんな細かい仕草を見ることは難しいので、どうしても声の宣告に頼ることになりがちだし、繰り返しになるが、ポール捕手がピアジンスキーにすぐさまタッグしていればあんなことにはならなかった。しかし、他の選手、監督、観客、テレビの前の視聴者にとってエディングス球審の一連のメカニックは大いに疑念を持たせるものになってしまったのではないだろうか。
これは憶測になってしまうが、エディングス球審は捕球点がよく見えなかったのだろうと思う。ビデオで見ても球審からは難しい角度に投球が行っているし、「音を参考にした」という彼のコメントからもそれは分かる。そもそも、捕球がしっかり見えていれば打者アウトを押し通しただろうし、ワンバウンドの確信があれば「ノーキャッチ」の宣告をきちんとしただろうと思われるが、実に曖昧な動きをしているところを見ると、捕球の瞬間には確信を持った判断はできていなかったのではないかと思わざるを得ない。
判断できなかったのならやはり「ノーキャッチ」の方が無難だから(あとで塁審に確認して変更することもできるし、捕手がタッグにいってくれれば万事解決する)、成り行きにしたのは悪くない選択だったとは思うが、あの握り拳だけが何とも余計だった。
こんな審判泣かせのプレイが、人々の注目を集める大試合で出てしまったことは、エディングス審判にとっては運が悪かったというしかない。私たちは今回の事件を、いわゆる「振り逃げ」の際に選手と審判がどのような行動をとるべきかを教えてくれた貴重なプレイだと考えた方がよさそうである。