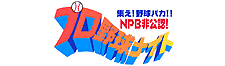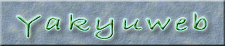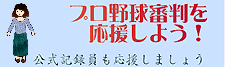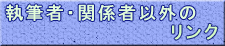にっぽん野球昔ばなし by 九時星
第四十六回 米国チーム来日す
慶応義塾創立50周年に当る明治40年、本来であれば全校、いや帝都中の注目を集めるであろう大行事たる早慶戦は前年の騒動が元で中止されたままでありまして、目標を失って呆然たる野球部員たちに「そう悲しむな。外国からチームを呼んでもいいし、また米国に行ってもいいじゃないか」と慰めたのは塾長でありましたが、それは早速実現したのでありました。明治40年10月、布哇(=ハワイ)セントルイス・カレッジ野球団と紹介されたチームであります。
ハワイにセントルイス大学?と疑問に思われた方もいらっしゃるでしょうが、これはあくまで自称でありましてその実体はセミプロチームでありました。当時日本人が対戦した外国人チームは居留地のアマチュア倶楽部かアメリカ東洋艦隊でありましたから、このセントルイス野球団は一段上の実力を持ったチームでありました。そしてこれが外国チーム招待の最初でありまして、また、その第一試合が日本人が初めて入場料を取った試合でもありました。
「この壮快にして前未曾有なる試合(=セントルイス対慶応戦)行わるるは来る(十月)三十一日午後一時なれば入場者はその心組にて左の数ヶ所に於て売り出される切符を買い求めるべし。(略)切符代は一等六〇銭、二等三〇銭、三等一〇銭にして早く買い求めざれば売り切れの恐れあるべし」
当時の新聞記事でありますが、果たして高いか安いか、当時の他の価格と比較してみましょう。動物園入場料五銭、映画館入場料二十銭、相撲観覧料(桝席一人当)七十五銭、コーヒー一杯三銭、たばこ一箱五銭、ビール大瓶一本十九銭、天丼(並)一杯十二銭、うな重(並)一杯三十銭、カレーライス(並)一皿五〜七銭、アンパン一銭、食パン一斤十銭、新聞1ヶ月四十五銭、巡査の初任給(月給)十二円、小学校教員の初任給十〜十三円、(値段の明治大正昭和風俗史〈正・続〉週刊朝日編)…比較するものによって大きく変わるのでありますが、三等十銭は現在の価格でおおむね500円〜1,000円程度ではないかと思われるのでありまして、庶民にも決して手が出ない金額ではないのでありました。
この試合は帝都の注目を集め、有料試合にもかかわらず車夫から陸海軍軍人、さらには皇族まであらゆる階層の人々がつめかけ、実に1万人もの観客を集めたのでありました。試合は延長13回、5対3で慶応の勝利となったのでありますが、当時来日していた『フィラデルフィア・イブニング・テレグラフ』のライト記者の記述によりますと「こうした試合を一〇銭(五セント)から六〇銭(三〇セント)で見られるのは安い」のだそうであります。 このセントルイスチームは滞在一ヶ月の間に慶応と5回戦い3勝2敗、早稲田とは3戦3勝の結果を飾ったのでありました。
さて翌明治41年になりますとセントルイスチームが返礼として慶応をハワイに招き、6月29日、ここに慶応チーム初の海外遠征が実現したのでありました。この遠征で慶応チームは見事14戦7勝7敗の好成績を残したのでありますが、負けてはならじと同年9月、早稲田は米国本土シアトルからワシントン大学チームを招待いたします。これは本物の大学チームでありますから先のセミプロ、セントルイス・チームよりやや実力に劣り、早稲田には3勝1敗でありましたが、ハワイから帰国した慶応には3戦全敗という結果でありました。
このように日米野球交流は徐々に盛んになっていったのでありまして、いよいよその年の11月、米国プロ野球選抜チームが日本にやってきたのであります。このチームは東京と関西でその強さを如何なく見せ付けたのでありますが、このチームのお話しに入る前に当時の関西の状況を見てみましょう。次回にっぽん野球昔ばなしは「神戸野球事情」です。
第四十七回 神戸野球事情
関西の野球といえば、これまでは三高、同志社と京都の話題ばかりご紹介してきたのでありますがそれに負けず劣らず歴史が古いのが神戸の野球であります。明治24年ごろに兵庫尋常中学に赴任した小森慶助校長が伝えたとされているのでありますが、一説には明治22年開校のミッション・スクール関西学院では開校当初から外人宣教師によって野球が伝えられていたとも言われております。
また、神戸には横浜と同じように外人居留地があり、横浜アマチュア倶楽部と同じような神戸クリケットクラブ(K・C・C)もあったのであります。如何せんその中心がイギリス・オランダ・ドイツなどヨーロッパ系でしたので野球を始めるのが横浜より遅くなったのでありますが、それでも間接的に神戸に野球を伝える役割は果たしていたのでありました。
ともあれ明治29年ごろには尋常中、関西学院のほかにも尋常師範、神戸商業、神戸中学などで野球が盛んになっておりまして、この年の10月には尋常師範対K・C・Cという関西初の国際試合が行われたのであります。ちなみに結果は31−8でK・C・Cの大勝、しかも3イニングのみとあっては、実力差は如何ともし難いのでありましたが、神戸の野球熱はますます盛んになっていくのであります。
明治30年ごろから各学校の野球好きの生徒が校外活動で組織したチーム、あるいは社会人の同好の士が組織したチーム、また、その両者の混成チームなどのクラブチームが盛んになり、「練習もする、試合もする、喧嘩もする、非常なる大繁昌にて、一時はヨヂムチンキの価が高くなりしとか」といわれるほどになっていったのでありました。(参考・神戸税関野球部六十四年の歩み、尾西東治郎著、コーセイ企画)
野球熱が盛んになると名選手も生まれてくるのでありまして、第一回早慶戦には神戸小から慶応普通部経由ではありますが慶応から高浜徳一が出場しておりまして、対する早稲田には後の渡米にも参加した神戸一中出身の名選手泉谷祐勝が出場していたのでありました。他には泉谷の実弟にして後の慶応主将佐々木勝麿、同じく慶応で活躍した神吉英三、高浜茂、早稲田で活躍した松田捨吉などを輩出するようになってきたのであります。そして神戸商業と神戸一中を中心として明治31年に結成された神戸倶楽部に彼らが参加するようになって一躍最強クラブチームとなったのでありました。
この神戸倶楽部で明治40年ごろ、エースとして君臨したのが菅瀬一馬でありまして、後に慶応に進み「長躯をひねって繰り出すアンダースローの熱球は日本人離れした偉力」(神戸の野球史<黎明記>、棚田眞輔著、六甲出版)と評される明治の大投手の一人でありました。
学生野球が全盛の東京においても当然ながら卒業生は出てくるのでありまして、卒業しても野球を続けたいと思うのもまた当然であります。そうするとクラブチームが出来るのもまた必然でありまして、明治41年秋、一高、慶応、早稲田、学習院のOBに現役選手も参加したクラブチームが結成されたのでありました。その名も東京倶楽部。神戸倶楽部の最強の好敵手の出現、といったところでありますが、それどころではない強敵がやってきたのであります。次回にっぽん野球昔ばなしは「職業野球団、来日す」です。
第四十八回 職業野球団、来日す(前編)
野球人気が高まれば野球用具の需要も高まるのでありまして、逆に言いますと野球用具の売り上げを上げるには野球人気を高めればいいということで、プロ選手を集めてチームを作り世界各国を巡業して野球人気を広げようという運動用具店も出てくるのでありました。
その嚆矢が日本最初のクラブチーム、新橋アスレチック倶楽部に用具やルールブックの支援をしたスポルディング社でありまして、明治21年(1888年)プロ選抜軍を編成し、イギリス、アイルランド、フランス、エジプト、セイロン、オーストラリア、ハワイを遠征したのでありますが、それから20年、フィラデルフィアに本拠を置きアメリカ野球界の使用球のほとんどをまかなう運動具店・リーチ社がプロ選抜チームを編成しいよいよ東洋遠征に向かったのであります。その名もリーチ・オール・アメリカン・スター・ベースボール・チーム。
当時の船旅でありますから、サンフランシスコから約20日かけて横浜に到着したのが明治41年11月21日、その翌日には早くも早稲田との対戦が始まったのでありました。この試合に先立ちシルクハットにフロックコート姿の大隈重信候が隻脚をささえるステッキをついてマウンドへと上がり、シルクハットを脱いでリーチ軍投手の帽子を被ると「オーバーシャツ(ユニフォーム)はいいかね」と冗談を言いながら二、三歩あるいて下手から投げたボールは転がりながら捕手のミットへ、それを審判がかねて準備の革製の小箱に収め大隈候に進呈、場内大拍手。これが日本初の始球式でありました。
さて試合は長旅の疲れも見せずリーチ軍が早稲田を5−0と一蹴すると、翌23日には東京倶楽部を19−1、慶応を3−0と連破、24日には東京連合チームに11−4、25日には横浜外人倶楽部に17−1、26日には横浜連合チームに11−0と大勝を続け、27日慶応を6−0、28日早稲田を3−0、29日慶応6−0、30日東京倶楽部8−5、翌12月1日は早稲田を13−2、2日慶応を15−2、3日早稲田を10−0、東京連合チームを3−0と、12日間に14試合して全勝、まさに無人の地を行く快進撃でありまして、日本野球の最高峰と自他共に認める早慶両校に対しても対早稲田4試合の合計点は31−2、対慶応4試合計は30−2と圧勝したのでありました。
「リーチ軍強し」の報は瞬く間に全国へと伝えられ、次の対戦地となる神戸では神戸新聞が「全米野球団の襲来」と題し、「神戸軍は如何に戦うか」という特集を組むほどの熱の入れようでありました。
記事に曰く、
「野球団を以て商売として居る米国に於ける最強のチームであって、此程東京の早稲田・慶応其他の野球団を片ッ端よりメチャメチャに叩きつけて其勢力の旺盛なる事とても我が球界の敵では無い」
「米国に於ける野球の商人中で選り抜いた強者で、ちょうど日本に於ける力士中の常陸山とか梅ケ谷・大木戸・放駒・太刀山・荒岩など云うようなものばかりであるから強いはず」
「神戸倶楽部に於てもかくの如き強敵に当るには、どうしても理想的チームを組織して当らねば大関に対して宮角力のチョコチョコが打ち掛かるようなもの」
というわけで神戸倶楽部が現役の早慶選手である倶楽部員を呼び寄せこの大敵との対戦準備を進めているとの記事と共に神戸倶楽部とリーチ・オール・アメリカンの選手を紹介し神戸市民の野球熱を高めるのでありました。次回にっぽん野球昔ばなしは「職業野球団、来日す」その後編です。
第四十九回 職業野球団、来日す(後編)
一試合平均9得点、日本最強と目されております早慶両校との対戦に限っても平均7点を越す得点を挙げ14試合全勝の快進撃で神戸に現れましたるリーチ軍、東京の試合から中一日置いた12月5日、まず第一戦の神戸クリケット倶楽部(KCC)を14−2で一蹴、改めてその実力を見せ付け、翌6日に神戸倶楽部との対戦を迎えたのであります。
「日は小春和の好天気、精鋭を以て関西に鳴れる神戸野球倶楽部が更に早慶の部員を呼び来りて強敵米軍と鎬(しのぎ)を削るべしとの呼声は熱球児の血を湧かしめて朝来東遊園地に押駆けたるもの無慮幾千名、流石に広きグラウンドも入る人を以て填(うず)もれん許りの大盛況を呈し本塁より右翼にかけたる桟敷と三塁より右翼に亘る一面は立錐の地なきまま、人山を築き開戦今や遅しと待構へたる光景は凄まじき頃、米軍先づ入場するに続いて神戸倶楽部は新調のユニフォームに英語にて神戸と赤抜きせるをまとひ、意気凛々として顕(あら)はれたり」(神戸新聞)
神戸の野球熱を高めたこの一戦、6−1でリーチ軍の勝利となったのでありますが、圧勝続きのリーチ軍を6点に抑えたエース菅瀬一馬の力投が光ったのでありました。
翌7日には神戸倶楽部と神戸高商、神戸商業、神戸一中などの連合軍がリーチ軍に挑んだのでありますが0−10で完敗、リーチ軍は戦績を17戦全勝とし、最後に神戸倶楽部、KCCを加えた紅白戦を行って日本を後にしたのでありました。
慶応の主力選手であり神戸倶楽部の選手としてもリーチ軍と対戦した佐々木勝麿と神吉英三によるリーチ軍評が神戸新聞に発表されておりますので以下にご紹介いたします。
「全米国野球軍とは同軍渡来以来しばしば戦って大に得る処があった。殊に米軍は我々の如き学生とは違って流石は野球を職業として居るだけあって、彼等のシグナルの巧妙なる事は驚くばかりで、我等学生団に於ても此暗号を用ひての駆引は行うがややもすれば敵に看破されて不覚の敗を招く事がある。然るに彼等の暗号は全く暗黙の間にチャンと呼吸が合って駆引を行って居るので、とても看破する事が出来ない。それであるから彼等の勝因は六七分まで巧妙なるシグナルによると云ってもよい。」
「米国に於ては近時左手で投球することが専ら行はれて居る。然し日本には未だ左利きの投手が無く、したがって左手の投球に対しての練習と云ふものがない。其処へ持って来て米軍の投手バアーンスは神に入るの技術と捕手とのシグナルに依って打者の欠点を看抜いて投球するのであるから堪らない。又球が速いと云うだけなら此方にも其覚悟があるから別段驚かないが、カーブの角度が鋭いのや速いと思ふ球が一間(約1.8m)くらい前から其速度を緩めてフワリと来る手品的な球には実に面喰ってしまふ。」
「捕手の活動と走者のスライデングは学ぶ処があった。三塁へ打った球を塁手が第一塁へ投げるとき捕手が第一塁に駆け付けて万一に備へるなどは我々が従来せらなかった所である。走者が足から先にすべり込むのは種々なる点に於て利益である。其他色々と彼等の為学ぶ処がすこぶる多かった。」
リーチ・オール・アメリカン・チームは日本野球界に大きな衝撃を与え嵐のように去っていったのでありますが、この頃、野球人気は高まる一方でありまして野球場を建設する企業も現れたのでありました。次回にっぽん野球昔ばなしは「羽田野球場と倶楽部対抗」です。
参考文献:神戸の野球史<黎明記>、棚田眞輔著、六甲出版
特別編:にっぽん野球の「引き分け」考
野球が日本に入ってきた当時は、現在とはずいぶんルールが違っており、圧倒的に打者有利、「打つ」スポーツだったのです。ですから明治初期のスコアでは20点、30点という得点も珍しくありません。このように得点が容易になっていくと、同点でゲームを終えることは非常に稀になります。やがて、学生チームの対抗戦、ついで中等学校野球大会、選抜大会、都市対抗などのトーナメント戦が盛んになります。これらはすべて勝つことが目的ですから、何らかの形で必ず勝者と敗者に分ける必要が出てきます。
ところが勝つこと以外に興行収入を得るという目的を持った「プロ野球」が始まります。ここでは「引き分け」でも興行収入を得るという目的を果たせることになります。しかし「引き分け」は興行サイドにとって現実的な選択肢ですが、対抗戦やトーナメント戦に馴染んだファンの意向に沿っていたかは疑問があります。実際に昭和11年に始まる職業野球リーグには「引き分け」が存在していましたが、学生野球に人気で大きく離されていました。戦時色が濃くなった昭和17年には「試合に引き分けがあるのはおかしい、勝負がつくまでやれ」という要望が軍部から出され(野口二郎著「私の昭和激動の日々」より)この年、延長28回という記録が生まれています。
それでは現在のプロ野球で行なわれている勝率制のもとで引き分けはどのように扱われているのでしょうか。例えば開幕から3連敗したチームがあったとします。このチームが次に引き分けると3敗1分で依然勝率0です。つまり引き分けは負けと同じことになります。ところがこのチームがその後3連勝したとします。3勝3敗1分で勝率は5割となります。それでは当初負けと同じだった引き分けが0.5勝になったのでしょうか。そうではなく、引き分けた試合は存在しなかったと考えるのが自然です。我々は順位確定上全く価値のない試合に入場料を払っていることになります。
野球よりも引き分けの発生率の高いサッカーでは勝ち点制をとっています。これは引き分け試合にも価値を持たせる考え方です。去年セ・リーグで行なわれた勝ち数制は「引き分けは負けである」と認定することにより、勝率制における「引き分け」の矛盾を解決することができたのですが、さすがにそこまで踏み込めず、勝率制と併用せざるを得なくなった結果、更なる矛盾を抱え込んで1年限りとなってしまいました。
勝率制のもとで「引き分け」に価値がないということは、例えば80勝60敗、勝率.571のチームと70勝50敗20分、勝率.583のチームのどちらが上位か考える時に、140試合消化したチームと120試合しか消化していないチームを比較していることになります。条件の違うチームを比較することに無理があるのは当然です。順位に影響する試合数を同じにすることでしか解決出来ないでしょう。引き分けを0.5勝として確定してしまう「擬似勝ち点制」と「引き分け再試合制」がこの問題を解決する手段として考えられます。ともに過去行なわれた実績がありますが、日本での野球の歴史を考えると「引き分け再試合制」のほうが「勝敗を明らかにする」というファン気質に受け入れられるのではないか、と思います。