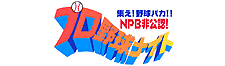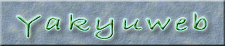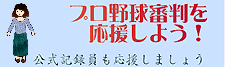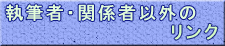にっぽん野球昔ばなし by 九時星
第二十六回 吾輩は迷惑である
郁文館中学が当時最強の一高にはじめて勝ったのが明治30年でありますが、その6年後、明治36年1月にロンドン帰りの英文学者がこの郁文館中学の隣接地に居を構えたのであります。ところがそこで予期せぬ災難に巡りあってしまうのでありました。何しろ強豪中学のことでありますから、放課後ともなりますと待ちかねたように野球の練習が始まるのであります。そして校庭に隣接する民家の宿命とでもいいましょうか、ボールがよく飛び込んでくるのであります。ボールが飛び込んでくればボール拾いがそれを探しに来るのは今も変わらぬ慣わしでありまして、少し神経質な英文学者先生が怒鳴りつけること再三であったようでありました。
明治38年1月号に英文学者先生の小説が載ったのであります。翌年8月号まで連載されたその書き出しは「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」…そう、英文学者夏目漱石先生のデビュー作でありました。この小説『吾輩は猫である』の中で当時の郁文館中学(小説では落雲館)の野球熱を描写した部分がありますので以下に引用しましょう。
「落雲館に群がる敵軍は近日に至って一種のダムダム弾を発明して、十分の休暇、もしくは放課後に至ってさかんに北側の空地に向って放火を浴びせかける。このダムダム弾は通称をボールと称えて、擂粉木(すりこぎ)の大きな奴をもって任意これを敵中に発射する仕掛である。(略)空地へ転がり落つるボールといえども相当の効果を収め得ぬ事はない。いわんや一発を送る度に総軍力を合わせてわーと威嚇性大音声を出すにおいておやである。」
「ある人の説によるとこれはベースボールの練習であって、決して戦闘準備ではないそうだ。吾輩はベースボールの何物たるを解せぬ文盲漢である。しかし聞くところによればこれは米国から輸入された遊戯で、今日中学程度以上の学校に行なわるる運動のうちでもっとも流行するものだそうだ。米国は突飛な事ばかり考え出す国柄であるから、砲隊と間違えてもしかるべき、近所迷惑の遊戯を日本人に教うべくだけそれだけ親切であったかも知れない。」
「ダムダム弾は近来諸所で製造するが随分高価なものであるから、いかに戦争でもそう充分な供給を仰ぐ訳に行かん。大抵一隊の砲手に一つもしくは二つの割である。ポンと鳴る度にこの貴重な弾丸を消費する訳には行かん。そこで彼等はたま拾いと称する一部隊を設けて落弾を拾ってくる。落ち場所がよければ拾うのに骨も折れないが、草原とか人の邸内へ飛び込むとそう容易くは戻ってこない。」
ダムダム弾とはイギリスが製造した銃弾の一種でありまして、あまりの殺傷力から漱石先生がロンドンに渡った1年前の1899(明治32)年、第一回ハーグ会議で使用禁止を宣言したという代物でありまして、漱石先生、庭に飛び込むボールをこの悪名高い銃弾になぞらえているのであります。もっとも漱石先生は一高時代が始まった頃には東京在住でありましたし、のちに赴任した熊本五中もまた野球熱の高いところでありました。しかも大親友があの、のぼさん正岡子規でありますから漱石先生が野球を知らないとか野球を敵視しているというのはあたらないでありましょう。
さて、小説ではボールを拾いに生垣をくぐって侵入した生徒を見つけ、「貴様等はぬすっとうか」と叱り始める所から話は続いていくのでありますが、それはまた『吾輩は猫である』本編を読んでいただいた時のお楽しみということで、郁文館中学から漱石先生へと少し時代を進めすぎました。そこでまた時計の針を少し戻しましょう。次回にっぽん野球昔ばなしは「一高渡米計画」です。
第二十七回 一高渡米計画
さて、時代は少し遡りまして一高が横浜アマチュア倶楽部に連戦連勝をしたのち、独立記念日の試合でアメリカ東洋艦隊選抜軍に敗れ、雪辱戦をしようにも相手が受けてくれず悶々とした日々を過ごしていたころのことであります。アメリカ・エール大学に留学していた旧知の人物から届いた一通の手紙が一高選手たちに大きな驚きと喜びをもたらしたのでありました。
『一高野球部の活躍は、その後当地に於いて非常に評判になっている。費府(フィラデルフィア)、シカゴ、紐育(ニューヨーク)の各新聞には、日本にベースボールが伝わったことを書き、続いて第一高等中学校がその覇権を握り、アメリカ東洋艦隊チーム、横浜在留民チームと戦って三勝二敗の成績は恐るべきものであると紹介したくらいで、私が日本を去ってから、一高チームの声望の隆々たるを遥かに聞き、大変喜んでいる。当地方に於いても、アメリカ以外で発達した野球、即ち日本を代表せる第一高等学校チームに多大の期待を持っている。もしも諸君が、一年を休んでアメリカに来る気があるなら私は喜んでこれを推薦し、旅費滞在費の支給できるようにするから至急御相談願いたい。委細は後便で御知らせする』
一高選手たちはこの手紙を持ったまま「万歳!」と叫んだのであります。ついに威名をアメリカにまで轟かせ、とうとう招聘されるとはなんと光栄なことでありましょうか。彼等は小躍りしながら野球部長の元へ報告に走ったのであります。野球部長もまた驚き、喜んで大急ぎで校長の元へ報告に…校長もまた大喜びで…そこにまた選手たちもやってきて…いやはや大変な騒ぎとなってしまったのでありました。しかし実際にいくとなると文部省の許可を得なければならないし、他にもいろいろ詰めなければいけない話もありまして、まずは翌日に全寮総代会を開いて意見を聞くということになったのであります。
選手たちが興奮のあまり眠れない夜を過ごした翌日、各寮、各運動部委員、部長、野球部先輩諸氏などによる総代会は開かれたのでありますが、名誉なことだからぜひ遠征すべしというものあり、学生の本分たる学業を一年も休むわけにはいかないというものあり、なかなか討議はまとまらずに残念ながらこの渡米計画は澪きりとなってしまい、その代りにエール大学を招待するという案でアメリカに返信を出したのでありました。
当時は航空便などというものはありませんから、手紙を往復させるだけでも何ヶ月もかかったのでありますが、再び届いたアメリカからの返信は、エール大学の渡日は到底不可能であるから一高が渡米する他に方法がないので何とか都合してもらいたいというものでありました。もちろん旅費滞在費を持つということも書かれております。ここに至って一高選手たちの渡米熱は再び高まってついに校長を動かし、校長は選手たちのために骨を折ることを約束したのでありました。
いざ渡米するとなると、いくら相手側の招待とはいえある程度まとまった費用を用意しないと万一の時にアメリカで一高の名誉を損ないかねないということで選手一同は諸先輩に支援を依頼に毎日歩きまわり、ついに支援を得ることに成功したのであります。
いよいよ準備万端、安心してアメリカに渡米の返事を送ることができると選手一同が喜び合っているその頃、文部省から学校側に学生を一年間休学させることについて注意してきていたのでありました。また、頼みの学内の空気も、最初の手紙がついてからあまりに時間が経ちすぎていたためか渡米に反対する者が多くなってきていたのであります。そして再び総代会が開かれ、『我が野球部がこれまで英名赫々として国威を外国にまでとどろかしたことは非常にうれしいことである。しかしそれに甘えて今渡米することは学生の本分を超えたものではないか』という意見が主流になり、渡米を応諾するはずの返信は渡米の断り状となってアメリカに送られ、ついに本邦初の野球チームのアメリカ遠征は幻となってしまったのでありました。
この、エール大学から一高に手紙を出してきた人物は明治学院白金倶楽部において天才と呼ばれた白洲文平氏でありました。少し寄り道になりますが白金倶楽部以降の彼の足跡を追ってみましょう。次回にっぽん野球昔ばなしは「天才・白洲文平、その後」です。
第二十八回 天才白洲文平、その後
名捕手にして「白洲のスマートキャッチ」として名高い文平さんは秀麗たる美丈夫でありましたが、また多くの伝説を残す豪傑でもありました。明治学院を卒業してのちにアメリカに留学して一高に渡米を勧める手紙を出したのでありますが、その後ハーバード大学に転じてここを卒業すると、次にドイツに留学するのであります。これはもちろん白洲家が代々儒者役として兵庫・三田藩に仕えてきたという家柄によるものでありますが、若き頃の文平さんはいつも仕込み杖を持って、肩で風を切って闊歩しているような青年であったそうであります。
帰国してからの文平さんは会社勤めをはじめるのでありますが、銀行に行っては「ソロバンなんぞはじいても世間は見えない」といってやめてしまい、紡績会社に行っては上役の奥さんに「お前さん」呼ばわりされたのが気に食わないといってやめてしまい、要するに会社勤めが性に合わなかった訳でありまして、勤めるのが性に合わなければ会社を作ってしまえとばかりに貿易会社白洲商店を設立してしまうのでありました。何を貿易するのかといいますと綿でありまして、これが大当たり、白洲商店の番傘に『二十世紀の商人白洲文平』と大書させ、文平さんは『白洲将軍』と呼ばれるほどの羽振りの良さでありました。
お金が出来ると道楽につぎ込みたくなるものでありまして、文平さんもご多分に漏れず道楽に入れ込むのでありますが、その道楽が『建築』。建築道楽とは何ぞや、といいますと要するに家を建てるわけであります。我々一般庶民のプラモデル作りと同じような感覚で。そのために腕は良いが大酒飲みで、酒で失敗したという宮大工さんを自宅に住まわせ、次から次へと壁の乾く間もなく建てるのでありました。しかもすべて日本屋敷。西洋暮らしが長かったので西洋館も建ててもよさそうなものでありますが、「汚い道から靴のまま上がったら汚れる」のが嫌なのだそうでして、そのくせ「俺は別だ」といって日本屋敷を靴のまま歩き回るのでありますから、息子の次郎氏から「これがほんとの傍若無人」と評されるのも当然でありましょう。そしてまたその一方では文平さんを「ほんとの意味のお洒落だった」とも評しているのでありました。
その次郎氏は大正8(1919)年にイギリス留学をするのでありますが、英ベントレー、仏ブガッティの2台の名車を所有し、『オイリー・ボーイ』(自動車狂)と呼ばれながらレースに夢中になるわけですから充分文平さんの血を引いているわけであります。
さて、絶頂期は長くは続かないものでありまして、昭和3(1928)年、世界恐慌の波を受けてあっけなく白洲商店は倒産してしまうのでありました。文平さん一家は財産を失って小さな家に移り住んだのでありますが、奥様は建築道楽で転々と引越しを繰返していた頃と比べて「これでやっと人並みの暮らしが出来る」と喜んだそうであります。
晩年の文平さんは阿蘇山の麓の小さな家でたった一人、愛犬と暮らして趣味の狩猟に興じていたそうであります。孤独なようでもありますが、やることを全てやり尽くして、使うものを全て使い尽くした人生だったのでもありましょう。ある日、近所のおばさんが掃除に来てみると、ベットの中で静かに息を引き取っており、ベットの下には棺桶が用意されていたのだそうであります。
その後、次郎氏は日本と海外を行き来する生活を続け、そこで駐英大使だった吉田茂氏と出会うのであります。そして戦争の始まる前年には「間もなく日米が開戦する。必ず日本は敗北する。しかし、敗北経験のない日本は最後まで抗戦して、東京は焼け野原になるだろう。そうなると、食料がなくなるから、俺は田舎で農業をやる」と宣言して会社を辞め田舎生活をはじめるのでありました。
戦後、吉田茂氏の片腕としてGHQとの交渉にあたり、「従順ならざる唯一の日本人」と呼ばれ、GHQホイットニー民生局長がやや見下して「白州さん、あなたはなかなか英語がお上手ですな。」と言った時にはすかさず「いえ、閣下。あなたも、もう少し勉強なさると、一流になりますよ。」と切り返し、サンフランシスコ講和会議で吉田茂首相の演説が英語で予定されていたのを「自国の言葉で」と日本語に替えさせたり、それでも「僕は政治家じゃない」といってその後二度と政治の世界に関わらなかったのでありました。
贔屓のチームは『大洋ホエールズ』、晩年までポルシェを乗り回し、昭和60(1985)年、83歳で亡くなった時の遺言書には『一、葬式無用 一、戒名不用』とだけ書かれていたのでありました。
さて、今回は野球からも明治からも少し離れてしまいました。次回はまた明治時代の野球の世界に戻ります。
参考文献;『白洲次郎』平凡社コロナブックス
『サライ』新緑特大号2004年5/6
第二十九回 東北の強豪
バンカラ官学といえば真っ先に浮ぶのが一高を代表とするいわゆるナンバースクールであります。明治26年にはハイカラ私学・同志社に敗れた三高の敵討ちをするべく京都遠征を試みながら果たせなかった一高でありますが、明治31年になりますと突如東北の雄・二高の挑戦を受けるのでありました。おりしも郁文館中学に連敗を喫し、帝都の覇者の面目丸つぶれとなっておりました一高野球部、この遠来の強敵に屈することとなったならば先輩諸氏に申し訳の立たない事態となっていたのであります。
仙台は明治20年頃に宣教師によって野球が伝えられたようでありますが、明治20年代も半ばになりますと二高が図抜けた強豪校として君臨しておりまして、押川春浪センセイが作った東北学院野球部などは一蹴されてしまうのでありました。それが明治30年を過ぎる頃には邦人中随一の強チームと評されるまでになっておりまして、それでは一つ腕試しとばかり一高との対戦を求め南下してきたのでありました。
衰えたりといえども天下の一高、よもや地方チームに負けることはあるまい、圧勝するであろうとの予想もありましたが、一高、二高とも鍛え上げた守備のチーム、試合は白熱した投手戦となりまして3−0、ようやくのことで一高が勝利したのでありました。勝ったとはいえ、点差もさることながら当時としてはあまりに少ない得点に一高野球部一同素直に喜べない思いでありました。一方の二高もまた遠征に勝利を得られなかったことを悔やみ、打倒一高に燃えて研究を重ねていったのであります。
翌明治32年、時至りとばかり二高から一高へ対戦の申し込みが届いたのであります。この年、一高は郁文館中学に3度目の敗戦を喫したばかりでありまして、この北の強敵を一蹴することで野球部の名誉を回復せんと、直ちに承諾したのでありました。前回が二高の遠征となれば今回は一高が遠征するのが儀礼であります。そしてそれは一高にとって初めての遠征となったのでありました。出発の日、野球部員と校友一同、千人にも及ぶ一群は「第一高等学校選手遠征」と大書された白旗をなびかせて上野の駅に向かったのであります。西郷どんの銅像の前で壮行の辞をうけ、満開の桜の下、「万歳」の声に送られて選手を乗せた汽車は一路東北・仙台へと向ったのでありました。
近年の不振を脱し名誉を回復したい一高、去年の雪辱を晴らしたい二高、どちらも負けられぬ一戦は1、2回に一高が7点を取ると2回裏には二高が4点、3回に一高が3点を取るとその裏二高は2点と、序盤から優位に試合を進める一高としぶとく追いかける二高の試合は4回、一高が1点を取ったその裏、二高は猛攻撃で一挙9点を挙げて逆転、その後の一高の反撃も及ばずついに凱歌は二高に上がったのでありました。
呆然として帰る一高選手たち、この屈辱を晴らすには勝利しかないとばかりまたもや猛練習に明け暮れるのでありました。さて、一高が雪辱を果たす日がくるのでありましょうか。次回にっぽん野球昔ばなしは「伏兵現る・その2」です。
第三十回 伏兵現る〜その2〜
都下においては郁文館中学に再三敗れ、仙台に遠征しては二高に敗れと、渡米計画が幻に終わって以来どうにも調子の出ない一高野球部でありますが、この頃になりますと都下の野球熱は益々盛んになっておりまして、学習院や独逸協会、更に関東では横浜商業に宇都宮中学なども強豪として名をあげてきていたのであります。腕を上げれば強いところに挑戦したいというのは世の常でありまして、彼等は一高に対して練習試合を申し込むのでありました。その第一が郁文館中学でありますが、続いて名乗りをあげたのが青山学院であります。
その頃の一高は二高への雪辱戦に燃えて日々練習に励んでいたのでありますが、都下の中学にそうそう負けてもいられないのでありまして、これを一蹴して二高戦への勢い付けにせんとばかりに挑戦を受けたのであります。しかしながら試合は青山学院のエース・橋戸信の力投もありまして、一高は思いもよらぬ敗北を喫するのでありました。こんなことでは二高への雪辱もままならないとばかり、直ちに青山学院との再戦を行なったのでありますが、再び敗れてしまったのでありました。
明治20年代半ばに始まった一高時代も明治30年代を迎えてついに終焉を迎えてしまうのでありましょうか。凋落を続ける一高野球部でありますが、これを挽回するには雪辱戦に勝利するしかないのでありまして、明治33年春、満を持して二高に試合を申し込んだのであります。これに勝利して覇権を取り返そうと意気込む一高野球部でありましたが、返ってきた返事は彼等を落胆させたのであります。すなわち一高が臥薪嘗胆、復讐試合に備えて練習に励んでいる頃に二高の運動体育に対する方針が一変し、いかなることがあろうとも他校との一切の対抗試合に応じず、となっていたのでありました。
一高は地団駄踏んで悔しがったのでありますが相手側が応じなければいかんともしがたく、これ以降一高二高の対抗戦は途絶えてしまったのでありました。こうなれば名誉を回復するためには更に強い相手に勝つしかないのでありまして、3年ぶりに一高は横浜アマチュアクラブに挑戦したのでありますが、終盤追い上げるも届かず、無念の涙をのんだのでありました。
低迷一高に光明は差すのでありましょうか、もはや一高時代は終わりを告げてしまったのでありましょうか。次回にっぽん野球昔ばなしは「大投手・守山恒太郎」です。
第三十一回〜はこちら。