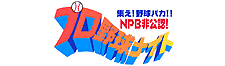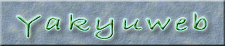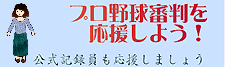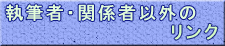俺が好きなスポーツ by ダイスポ 日本スポーツ物語編
●日本スポーツ物語 日本F1物語 〜その2〜
■連載第30回 「日本F1物語:第6話 <日の丸>」
■連載第32回 「日本F1物語:第7話 <公式予選>」
■連載第34回 「日本F1物語:第8話 <ホンダ・ミュージック>」
■連載第36回 「日本F1物語:第9話 <ギンサー獲得>」
■連載第38回 「日本F1物語:第10話 <迷走>」
連載第30回 「日本F1物語」:第6話 <日の丸>
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。
「日本F1物語」、今月はその第6回です。1964年、ホンダF1チームのグランプリ・デビューが遂に決まりました。彼らはどうやって、初戦のドイツGP出走へ漕ぎ着けたのでしょうか。皆さんと一緒に振り返ることにいたしましょう。
ホンダF1チームの指揮官である中村良夫と、ドライバーに抜擢されたアメリカ人ドライバーのロニー・バックナムは、実戦に投入するRA−271の完成を待たずに、ヨーロッパへと旅立っていった。実際にレースに出走するまでには、まだまだやらないといけないことがたくさんあったのだ。FIA(国際自動車連盟)や、各国グランプリ開催者への出場手続きなどである。
F1の経験が無いバックナムにとって、欧州のサーキットは未知の場所であった。それに同じモータースポーツであっても、米国と欧州のそれは大分雰囲気が違う。まずはヨーロッパのレースの雰囲気に慣れること、その独特のムードに飲まれないことが大切であった。
中村はパリにある、FIAの本部に向かった。ここで中村が解決すべき問題がひとつあった。それはホンダF1カーのカラーをどうするかである。現在のF1カーは、それぞれのチームに付いているスポンサーの色を施してある場合が殆どだが、当時はそれぞれのチームが所属する国の、言わば「ナショナル・カラー」を塗るのが常識であった。だがその時点では、日本のF1カーにおける色は決まっていない。
本田宗一郎の希望は、RA-270で使用したような、全面ゴールド塗装であった。しかしこれは、FIAの幹部によってあっさり否定されてしまう。ゴールドは、黄金の国、南アフリカのものと既に決まっているというのだ。したがってホンダがゴールドを使用する為には、南ア側の了承を得ないといけない。そんな時間的余裕は全く残されていないので、この案は引っ込めざるを得なかった。
それなら、と中村が提案したのは、白であった。正確には、アイボリー・ホワイトである。しかしその幹部はこの案にも難色を示した。なぜなら、ドイツのポルシェがシルバーを採用しており、サーキットで白とシルバーを混同する可能性があるからだ、という。
白もだめなら、一体どうすればいいのか・・・思案していると、幹部が面白い事を言い出した。「それなら白地に、日の丸の赤を施してみればどうだね?これなら、どこから見ても日本の車だと分かるじゃないか」
この一言で、ホンダF1のボディには、白地に赤い日の丸が描かれる事に決まったのであった。中村は日本に電報を打って、パリにおける決定をすぐに知らせた。
それからも中村は精力的に働き、グランプリ転戦の為の手続きを進めていった。ここでも、全てが手探りである。道無き道を歩く、まさにそんな言葉がピッタリ来る中村達の奮闘ぶりであった。
そうこうしているうちに、実戦用RA-271が完成。7月12日、羽田空港を飛び立ったRA-271は、ニューヨークを経由してアムステルダムに到着した。中村は、FIAとの取り決めどおりにカラーリングされた「日の丸F1カー」を見て、まんざら悪くないな、と思った。
しかしレーシングカーの命はボディのカラーではない。いかに走るか、である。その日からデビュー戦本番に向けてのテストが始まった。ここでも中村は手ごたえを感じていた。もちろんF1デビューのバックナムがはじき出すタイムと、トップチームの出すタイムにはまだ歴然とした差があった。上位入賞などは望めないし、第一完走の可能性も低かった。しかしそれでも、RA-271が持つ能力を十分に引き出して、さらに能力を高めていく必要があった。それにバックナムの能力は予想以上のものであり、この点でも中村は勇気付けられた。
そして遂に、ホンダF1チームはドイツ入りを果たした。ドイツで彼らは、思いのほかの歓待を受ける。当時のドイツ人にとっては、まだ日本は「かつての同盟国」と言う意識が強かったのかもしれない。また中村は「ゼロ戦の設計者で、柔道の達人」と言う紹介をされていた。実際には、ゼロ戦はエンジンの開発を少しやらされただけだ、それに柔道の達人なんてとんでもない、剣道初段だよ…中村はいろいろ説明したが、その辺は大らかなものであった。またジャーナリスト達は、ホンダのF1エンジンが奏でる音をこぞって誉めたてた。
「美しいね、まるでミュージックみたいだ」。
ドイツグランプリの開催地、ニュルブルクリンクに入ったホンダチームは、本番用の実戦テストを始めたが、そこでも苦闘の連続であった。とにかく全長22kmの長大なコースである。このままでは完走はおろか、出走さえ不可能になってしまう。中村は全力を尽くして、マシンを出走可能な状態に持っていくよう、チームの全員にハッパをかけた。
しかしマシン以外にも、この時ホンダは大きな問題を抱えていた。F1ドライバーズ協会の会長から「未経験のバックナムが、未経験のホンダでこのコースを走るのは無謀だ。今回の出走からは、ホンダを除外した方が良い」という意見が出されていたのである。
いかがでしたか?一難さってまた一難、さぁレース当日は一体どうなるのでしょう。
しかし、お時間が参りました。続きは、次回の講釈で。
(参考文献・資料は、本連載終了時にまとめて掲載します)
連載第32回 「日本F1物語」:第7話 <公式予選>
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。「日本F1物語」、今月はその第7回です。
ホンダF1チーム、いよいよ初のグランプリ出走が目前に近づいてまいりました。しかしそこには、思わぬ落とし穴が・・・果たして、彼らの最初のレースは、一体どのようなものになったのでしょうか。皆さんと一緒に振り返ることにいたしましょう。
1964年、7月31日。ホンダF1チームにとって初の実戦となる、ドイツGPの開幕である。この日はまず、最初の公式予選が実施された。しかしロニー・バックナムが操るホンダRA−271は、午前中からいきなりのトラブルに巻き込まれた。気化器(キャブレター)の不備が顕著なのである。ホンダチームの指揮官である中村良夫は、貴重なプラクティスの時間を費やして、キャブレターの調整作業を行わせた。しかしその作業も、またもや難渋を極めた。
何しろ、12気筒エンジンである。全てのキャブレターを満足行く内容にまで調整するのは、大変な時間がかかる。しかも、貴重な午前のプラクティスをまるまるこの調整作業に費やしても、十分な調整を完了させることは出来なかった。
午後に入ると、ホンダは再びRA−271をサーキットに出した。規定により、最低5ラップの周回を行わないと、決勝に進むことは出来ないからだ。キャブレターのトラブルを抱えながらも、イチかバチかの賭けに出たのである。
しかし、この賭けがまたも裏目に出た。バックナムは、コース上で車体を傷つけてしまったのだ。
この整備にもまた、ほぼ一昼夜かかる事になってしまった。複雑な車体構造のRA−271は、整備に大変な時間を要する。経験不足が招いたミスとはいえ、記念すべき初レース初日は、僅か1ラップで終わってしまったのである。ある程度予想していたとはいえ、ホンダは早くも断崖絶壁のピンチに立たされてしまった。
翌日も、ホンダの苦闘は続いた。なにしろ、5ラップの周回は絶対にクリアしないといけない。しかし、ドイツGPの行われるニュルブルクリンクは、1周22.8kmもある巨大なサーキットである。ここで5ラップを走るのは、まだよちよち歩きのひよっこであったホンダには、まさに決死のチャレンジに近いものであった。案の定、RA-271はまたもトラブルを起こしてしまった。しかも昨日は、バックナムがなんとかピットまで車を持って帰って来る事が出来たが、今度はコース上で完全に立ち往生してしまったのである。今度ばかりは、さすがの中村も頭を抱えてしまった。
マシンがレッカー車により戻ってきたにしても、午後から整備を初めて終了する可能性はほぼ不可能であった。まさに、万策尽き果てたとはこのことであった。
しかもこの頃、中村たちの知らないところで、ホンダのマシンをレースに出さないよう働きかける動きがあった。F1ドライバーズ協会の会長であるジョー・ボニエが「未経験のバックナムが、未経験のホンダでこのコースを走るのは無謀だ。今回の出走からは、ホンダを除外した方が良い」という意見を出していたのである。しかしこの申し入れは後に撤回される事になった。バックナムの先輩である、アメリカ人レーサーたちがバックナムのレーサーとしての適応性を保証してくれたからである。
そんなことは知る由も無かった中村たちは、なんとか出走に漕ぎ着ける為奔走した。確かに、現状は絶望的だ。だがここで諦めてしまっては、一体何のために今まで苦労してきたのか、全く意味が無くなってしまうからだ。中村は主催者の元へ行き、公式予選の後に更なる特別セッションを設けて、その間に5ラップを消化する旨申し出たのである。もうなりふり構ってはいられなかった。
そして、中村のこの申し出は受け入れられた。主催者側としても、懸命に作業を続けているホンダを何とかレースに出したいと思っていたのだ。またドイツ人ドライバーの乗るマシンもトラブルで、まだ周回を終えていないことも幸いした。特別セッション開催が認められ、バックナムは慎重にマシンを操り、遂に規定周回数を満たす事に成功したのである。中村は、ほっと胸をなでおろした。
だが、翌日の決勝に向けて、クルーたちの必死の作業は続いた。何とか出られるからには完走したい、無様なレースはしたくない。作業は、夜を徹して行われたのである。
さぁ、いよいよレースが始まります!日の丸F1、遂にニュルブルクリンクの森に見参!
しかし、お時間が参りました。続きは、次回の講釈で。
(参考文献・資料は、本連載終了時にまとめて掲載します)
連載第34回 「日本F1物語」:第8話 <ホンダ・ミュージック>
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。「日本F1物語」、今月はその第8回です。
初陣を飾った、ホンダF1チーム。今回からはアクシデントに次ぐアクシデント、予期せぬ事が次々と起こり波乱の幕開けとなった1964年シーズンの、彼らのその後の足跡を今回は追っていくことにしましょう。しかしその前に、デビュー戦のドイツGPの模様を今一度おさらいしてみましょう。このドイツGPにつきましては、既に本連載の第1回でご紹介しておりますが、今回はダイジェストで振り返ってみたいと思います。
やっとの思いで出走に漕ぎ着けたドイツGP決勝。サーキットに姿を現した日の丸F1のマシンを見て、場内のスタンドを埋めた観衆から、期せずして大きな拍手が沸き起こった。しかしホンダF1チーム監督の中村良夫には、その余韻を楽しんでいる余裕など全く無かった。いまのRA-271のセッティング状態で、この長大なニュルブルクリンクのコースを完走出来るとは思わない。もちろん、入賞などは夢・・・しかし、とにかくマシンのポテンシャルを充分に引き出さぬまま、リタイアする事だけは避けたかった。なんとしても、出来うる限り車を走らせて、可能な限りの情報を得たかったのである。いまは何も考える事など出来ない、とにかく突っ走れ、それだけであった。
しかし無名のアメリカ人ドライバー、ロニー・バックナムが操るRA-271は、徐々にその秘めたパワーを発揮していった。プラクティスでさえ満足にラップを重ねる事ができなかったマシンが、なんと本番で警戒に順位を上げていくではないか。この光景を目の当たりにして、中村は自信を深めた。確かにこれまで、何一つ結果を出していないマシンではあるが、ホンダのF1カーはきちんとした条件さえ整えば、百戦錬磨の他チームを相手にしても充分に戦えるのである。その事をいまバックナムが証明しつつあった。特にホームストレッチの直線では、あの名ドライバー、ジム・クラークが操るロータスにも決して負けないだけのスピードを誇っていた。そしてバックナムは、遂に9位まで順位を上げてきたのである。いける、いけるぞ、いける所まで行け!中村は「自信が確信に変わる」手ごたえを掴んでいた。
だが、そこまでであった。バックナムは終盤の12周目でマシンを大破してリタイアしたのである。心配した中村が現場に駆けつけてみると、バックナムは無事でありほっと胸をなでおろした。中村は完走できなかったバックナムをなじるどころか、感謝の気持ちで一杯であった。この不完全な状態の整備で、よくここまで走ってくれたものだ。とにかく、初戦としては充分すぎるほどの手ごたえを掴んで、ホンダF1のデビュー戦は終わった。確かに完走する事はできなかった。しかしホンダはいま、F1の歴史に大きな第一歩を記す事が出来たのである。
中村は早速、次のイタリアGPに向けて準備を始めた。次戦までには、まだ1ヶ月の時間がある。今のうちにやれる事を全てやっておく必要があった。まずクラッシュした1号機は、もう次のレースでは使い物にならない。だから2号機を急いで完成させてもらい、現地まで送り届けてもらわないとならなかった。1号機の事故車は、逆に日本に送り返さないといけない。また今回のレースで得た貴重なデータを、翌1965年に投入する新しいマシンに反映させる必要がある。こちらの検討もあわせて行う為、中村の日常は相変わらず多忙であった。
2号機の到着は遅れた。日本からヨーロッパに発送するわけだから、もともと時間がかかる。。またようやく到着したマシンにも問題があった。イタリアGPの行われるモンツァのコースは高速コースであるが、このコースをRA−271がエンジン全開で走ると、エンジン水温・油温共にかなり上昇し、冷却能力が不足している事が分かった。この問題もまた、中村を大いに悩ませた。
とはいえ、ホンダF1マシンの加速は素晴らしく、エンジンはモンツァの高速ストレートを素晴らしい高周波の排気音を立てながら快走した。この音を聞いて、ジャーナリストは「ホンダ・ミュージック」と名づけたのである。以前にもRA-271のエンジン音をそう表現したジャーナリストがいたが、実際にその呼び名で報道されるようになったのは、モンツァが最初だったという。
このレースではバックナムが巧くマシンを操って予選10位と大健闘したが、決勝では13周目でまたもリタイアとなった。だが前回以上の手ごたえを中村は感じていた。「これでいいのだ、完走の必要は無い。今はあくまで、マシンのポテンシャルを確かめることが必要なんだ」。そしてマシンは潰しても良いが、ドライバーは決して潰れてはいけない。中村はバックナムにこう言い聞かせていた。
2度の失敗を経て、ホンダF1チームは様々なことを学ぶ事に成功した。完走こそしないものの、日の丸F1は少しずつ、その存在感をサーキットで高めていたのである。
いかがでしたか。さぁイタリアGPの後中村は、ある「次の手」を打ちます。その「次の手」とは・・・
しかし、お時間が参りました。続きは、次回の講釈で。
(参考文献・資料は、本連載終了時にまとめて掲載します)
連載第36回 「日本F1物語」:第9回 <ギンサー獲得>
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。「日本F1物語」、今月はその第9回です。待望のF1デビューを果たしたホンダF1チームはなかなか結果が出ないながらも、着実に進歩を遂げ始めていました。ホンダが狙う次のステップは、一体何だったのでしょうか。皆さんと一緒に振り返ることにいたしましょう。
モンツァで行われたイタリアGPから次のアメリカGPまでには約1ヶ月の時間があり、アメリカに移動した中村らホンダチームは、これまでのレースで発生した問題点の改修作業に入っていた。これまでのレースでは完走こそ出来なかったものの、中村は手ごたえを感じていた。問題点を改善さえ出来れば、きっとホンダはF1で勝つことが出来る・・・
そして中村には、もう一つの重要な仕事があった。BRMチームのセカンドドライバー、リッチ−・ギンサーの獲得である。ギンサーも、バックナムと同じアメリカ人ドライバーであり、フェラーリやBRMで豊富な経験をつんでいた。ただし、いまだ優勝経験が無かった。
中村はギンサーのマシン開発能力を高く評価していた。バックナムはよくやってくれてはいるが、やはりF1の世界では経験の無い新人である。技術のみならず、レースを勝ち抜く上で必要な闘志や勇気も充分持ち合わせてはいる。しかし、F1ドライバーとして最も重要な、いまのマシンにある問題点を発見し、改良点をエンジニアに報告する事はまだ出来なかった。つまり完成されたマシンを速く走らせる事は出来たとしても、車をより速く走らせるように仕上げていくマシン熟成能力に欠けていたのである。それは、やはり経験を積んだベテランの仕事であった。
またギンサーも、自分の力量に自信を持ちながら、何時までもチームのセカンド・ドライバーである現状に不満をもっていたから、中村の誘いに乗りホンダへの移籍を承諾した。ギンサーにとっても、この移籍は新しい自分のキャリアを築き上げるために必要なチャレンジであったのだ。俺だってグランプリの主役になりたいし、それだけの実力を持っていると自負している。しかしこのまま、何時までもヨーロッパのチームに所属していたのでは、外様であるアメリカ人の自分はトップに立てない。新興チームで実績は無いが、新しいホンダで優勝を勝ち取ってみたい。
幸いBRMとホンダの交渉も上手くまとまり、ギンサー移籍が決定した。
その間にも、ホンダはアメリカGPに出走を果たした。だがマシンの冷却能力不足はまたもや解消する事が出来ず、オーバーヒートを起こして50周目でリタイアした。まだ次のメキシコGPが残ってはいたが、中村はこのレースに出走せずに帰国する事を決めた。現在の状態でメキシコに行っても、これ以上得るものは少ない。それよりもこのオフを利用して、来シーズンに向けたマシンの開発作業に時間を割いたほうが得だと判断したのである。そのマシンは、F1を完走する事が目的のマシンではなく、あくまでも勝つことを前提において開発されねばならなかった。幸いにもドイツ、イタリア、アメリカと性格が異なる3つのコースを走る事によって様々なデータを得る事が出来たし、マシンを作り上げる能力に優れたギンサーを獲得する事も出来た。バックナムは経験こそ少ないが、前述のように速いマシンを走らせる能力には長けている。
1月にロータスのコーリン・チャップマンとの提携が破談になってから、まだ9ヶ月しか経っていなかった。中村は、この短い期間でよくこれだけの事が出来たものだと感慨深かった。「ホンダは、ホンダ自身の道を歩む」。チャップマンに返答した通りのことを、自分たちは成し遂げてきたのだ。これまでは、まるで暗闇の中を手探りで、誰の力も借りずに走り続けてきただけだった。しかし今、中村達には、自分たちが目指すべきゴールがはっきり見えていた。それは、より実戦に適したマシンの開発を行い、グランプリを転戦しながら、円滑なチーム運営により、ホンダのドライバーを表彰台の一番高いところに立たせることであった。
こうしてホンダは、F1参戦最初のシーズンを終えたのである。
ところが。
帰国した中村を待ち受けていたのは、本田宗一郎のカミナリであった。
「おい、なんだあの無様な成績は!なぜお前たちは勝つ事が出来ないんだ」
この本田のせっかちさには、さすがの中村も唖然とした。まだ、初年度じゃないか。どうしていきなり勝てるなんて事が出来るんだろう。相手は百戦錬磨、グランプリで勝つための知識と技術を兼ね備えた本物のプロフェッショナル達。対するこっちは、何もかも手探りでマシンを作り上げて来た、未熟な集団に過ぎないではないか。
しかし、そんな理屈が通用する相手ではない。さんざん怒鳴られてしまった中村は、これはもうますます、来年勝利を収める以外に自分たちの生きる道が無い事を悟ったのであった。
いかがでしたか、次回はいよいよホンダF1参戦2年目に入ります。今度こそ中村達は、念願の初優勝を遂げる事が出来たのでしょうか?
しかし、お時間がまいりました。続きは、次回の講釈で。
(参考文献・資料は、本連載終了時にまとめて掲載します)
連載第38回「日本F1物語」:第10回 <迷走>
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。「日本F1物語」、今月はその第10回です。F1参戦2年目を迎えたホンダF1チームは、悲願の初優勝に向けて突き進んでいましたが、開幕を前に思わぬ事態に遭遇します。それは一体何だったのでしょう。ホンダは、無事グランプリ制覇を成し遂げることが出来るのでしょうか。皆さんと一緒に振り返ることにいたしましょう。
経験豊富なリッチ−・ギンサーをチームに加え、いよいよ勝負をかけるはずだったホンダだが、1965年シーズンは最も重要な人間を欠いたまま開幕を迎えることになった。ここまでホンダの核となって働いてきた中村良夫が、監督の座から退く事になってしまったのである。会社組織の一員である以上、上層部の決定には従わないといけないが、しかしこの決定は中村にとっても意外であり、また心外であった。昨年、ホンダがロータスとの提携を破棄されてから、自分たちの力だけで曲がりなりにもグランプリ参戦を果たせてきたのは、中村の活躍に拠る所が大きかったからである。自分と言うキーパーソンを外して、一体ホンダF1チームはどうなってしまうのだろうか?中村は不安であった。
監督の後任には、2輪グランプリの経験が豊かな関口久一が就任した。関口自身は優秀なメカニックである。しかし、だからと言ってそれだけでは、F1という舞台は勝ちきることができるものではない。これは中村自身が身をもって体験したことであった。来季から中村は技術面でのサポ−トとしてのみF1プロジェクトとかかわり、チーム・マネジメントの先頭からは身を引く事になった。
そのシーズン開幕に先立つ64年の11月、有力ドライバーのジャック・ブラバムがタイヤメーカー、グッドイヤーの担当者を連れて日本にやって来た。これまでF1のタイヤはダンロップ社の独占だったが、来年からはグッドイヤーが参戦しブラバムもダンロップから乗り換えるという、ホンダもグッドイヤーのタイヤを使って見てはどうだというのだ。これは中村にとっては渡りに舟であった。グッドイヤーがどこまでやれるかは未知数だが、技術力に問題はあるまい。また新興チーム・ホンダに対するダンロップの扱いは他の欧州チームより悪かったが、グッドイヤーはホンダに対するサポート体制もきちんとすると言う。中村はグッドイヤーへの移行を決めた。そして来季へのお膳立てを全て整えたところで身を引き、本来の仕事場である研究所の設計室に戻った。未練が無いわけが無い。F1チームは、自分が手塩にかけて育てた大切な存在だ。ギンサーやバックナムのテストだって見たいに決まっている。しかし自分が行く事で。メンバーの中に混乱をもたらしたくない。中村ははやる気持ちを必死に押さえつけた。
中村がいなくなって、案の定ホンダチームは迷走を始めた。まずギンサーがNo.1ドライバーとしての我とエゴをむきだしにし始めた。テストで車を独占し始めたのである。確かにギンサーに期待したのはマシンの熟成ではあるが、だからと言って、バックナムに走る機会を与えないというのはやり過ぎだ。開幕前の鈴鹿テストで、ギンサーが200ラップを超える走り込みをやったのに対し、バックナムはわずか数ラップを消化しただけであった。
これは明らかに異常である。それに中村の構想では、ギンサーでマシンを育てて勝負をかけるのはバックナムだったのだ。この前提が、もうテストの段階で崩れてしまっている。しかもそれを許すチームの運営にも問題があるといわざるをえなかった。当然バックナムは面白く無い。そのせいもあってかテスト中に事故を起こし、足を複雑骨折してしまったのである。この事故を含め、昨年から続くリタイアを見た本社からは、バックナムのドライバーとしての技量を疑問視する声が上がっていた。しかしこれは中村からすれば見当違いも甚だしかった。バックナムがリタイア覚悟で走ってくれたからこそ、チームに貴重なデータをもたらすことが出来たのであり、安全重視の走行では決してそうはいかなかった。中村は監督として、車を潰す事を恐れず思い切って走る事をバックナムに要請した結果のリタイアであり、これをバックナム個人の責任にすることなど許す事ができなかった。
6月のベルギー・グランプリで、ギンサーは無事6位入賞を果たした。しかし、ホンダはこの際正式エントリーが出来ておらず、入賞が無効にされてしまう可能性があった。この時は中村が不安のあまりサーキットに来ており、彼が率先して事務局と掛け合い事なきをえたのであるが、こんな不手際を起こしてしまうチームにも中村は憤りを感じていた。それに6位入賞ごときでメンバーが喜んでいるのも不満だった。上手くやれば入賞どころか、勝てたと思うからだ。そしてベルギーGPに続くフランスでは、ホンダはギンサー、バックナム共にリタイアに終わった。電気系のトラブルであった。レース後、ギンサーは「ナカムラ、あなたはチームに必要な人間だ。もっと積極的に、チームに介入してくれないか」と言った。中村は、チームに混乱を起こしたくないという理由からこの申し出を断った。
しかし、中村以上にこの事態を怒っている人間がいた。優勝以外は、2位も6位もないと考えている男が・・・言うまでも無く、本田宗一郎であった。
いかがでしたか。迷走を続けるホンダF1チームに対し、中村、そして本田宗一郎はどのような行動に出たのでしょうか。65年のうちに、ホンダは優勝を勝ち取れたのでしょうか?
しかし、お時間がまいりました。続きは、次回の講釈で。
(参考文献・資料は、本連載終了時にまとめて掲載します)
※第11話〜最終16話はこちらから。