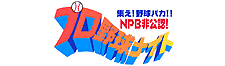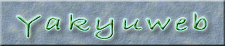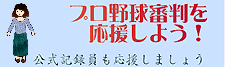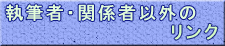プレイボールとゲームセットの間に by 粟村哲志
第16回 「サプライズ!」
野球の試合には、たとえばサッカーやラグビーのような制限時間がないから試合終了時刻の予想はできないが、それでも9イニングの試合なら2時間半から3時間程度で終わるのが普通である。その間、審判員は何を考えて任務についているのか?
多くの場合、それは「予測」に費やされる。審判をやっていない人には分かりにくいと思うので、少し丁寧に説明しよう。
たとえば、無死走者一塁という状況になったとしよう。私が一塁塁審を担当していたとしたら、およそ次のようなことを考える。
1.外野に位置していた二塁塁審が内野内に位置するので、外野飛球に対する責任分担が変わること
2.そして実際に外野飛球が飛んだときのフォーメーションの確認
3.一塁走者に対する投手の牽制とボークの監視
4.一塁走者に対する牽制からランダウンプレイ開始の可能性
5.内野がバントシフトをしくかどうかの確認
6.内野ゴロが発生した場合、ダブルプレイになるか一塁のみのプレイになるかで位置取りを変えること
7.一塁側・右翼側へのファウル飛球に対するスタートの仕方
8.ライン際のフェア/ファウルの判定に対する心構え
9.ハーフスイングに対する心の準備
細かいことをいえばキリがないのだが、この程度のことは瞬時に「予測」しなければならない。
ここでひとつ言っておきたいのは、この「予測」は「決めつけ」ではないということである。プレイは生き物だから、一瞬先にどのようなことが起こるかは全く分からない。「予測する」というのは、「次はバントで来るに違いない」とか「この打者ならゴロになるのではないか」などと予測範囲を狭めてしまうことではなく、起こりうるあらゆるプレイとその結果を想定し、そのどれが起きても対処できるように心の準備をしておくことである。
米国審判学校の校長であるジム・エバンス氏が繰り返し言うことのひとつに、「審判員にとって最大の敵は『驚くこと』である」というものがある。けだし名言であるとつくづく思い返す。実際の試合で自分自身が「失敗した」と思う、その一番大きな原因は、何か予測もつかなかったようなプレイが発生して驚いてしまったり、何らかの油断があって驚いてしまったような場合が圧倒的に多い。
ジム・エバンスが大リーグ審判員としての現役時代、ヤンキースタジアムで一塁塁審を担当していてこんなプレイがあったそうだ。走者一塁で一塁手の前に地面すれすれのライナーが飛んだ。そのライナーは結果として際どいワンバウンドでのキャッチだったらしいのだが、その判定を行うのはジムの仕事である。そこでまずフェア地域をポイントしてから両手を「セーフ」のように広げてノーキャッチのコールをした。そして、ボールをつかんだ一塁手がそのままベースを踏んだので打者走者にアウトの宣告をした。しかしダイレクトキャッチと勘違いして一塁ベースに滑り込んで戻ってきた一塁走者に対してはセーフのコールをしなければならなかったという。
その間わずかに数秒。たった2秒か3秒の間に「フェア」「セーフ」「アウト」「セーフ」のゼスチュアをしたジムに対して、地元放送局のアナウンサーは「ジム・エバンスは難しいプレイに対して混乱したため、たくさん判定を出しておけばどれかひとつは正解すると思ったのではないでしょうか」とコメントしたそうだが、実際はそうではなかったのである。
以前にこのコラムで紹介した「脱げたヘルメットに投球直撃事件」や「投手の投球が球審の顔面に直撃事件」なども、実際に驚いたけれども何とか上手く対処した成功例の紹介だったといえるかもしれない。もちろん、今までの審判経験の中で、私も多くの失敗をしてきた。そして、これからも続く審判人生の中で、どれだけの試合を裁き、どれだけの難しいプレイに直面するか分からない。しかし、常に「驚かないこと」を心に銘じてフィールドに立ち続けようと思っている。
第17回 「失敗した後の対応」
一塁塁審を務めていたある試合でのこと。
走者満塁のケースで、投手がセットに入りかけて動作をやめてしまった。完全なボークである。私はすかさず投手を指差して「That's a balk!」と宣告した。他の審判から同調のコールはなかったが、プレイは完全に止まっているので私はそのまま走者を進めた。すなわち、三塁走者に得点を与え、二塁走者を三塁へ、一塁走者を二塁へ進めたわけである。
ここまで終わったところで、何かグラウンド全体の雰囲気がおかしいことに気がついた。投手は怪訝そうな顔で私の方を見ているし、守備側のベンチからは「タイムがかかっていたよ」と口々に疑問の声があがっている。まさか、と思って球審の方を見ると、困ったような顔をしてこちらに歩み寄ってきていた。
私は球審のもとに駆け寄り、確認した。
「タイムをかけたんですか?」
「打者に要求されたので...」
「声が聞こえませんでしたが」
「声は小さかったかもしれません...」
「でも間違いなくかけたんですね?」
「かけたのは間違いないです」
仕方がないので私はボークを取り消し、走者を元に戻した。幸いなことに、攻撃側からクレームはつかず、トラブルに発展することはなかった。もっとも、審判として恥ずかしい不手際であったことは事実である。
責めるつもりは全くないが、この件に関しては球審の落ち度がいくつかある。まず第一に、こういった大事な場面でのタイムの宣告は、ことさらに大きな声とゼスチュアで行わなければトラブルの原因となりかねない(今回は実際になりかかったわけだが)。現実問題として、この場面で私の仕事は投手を監視すること「だけ」である。声が聞こえなければタイムに気づくことは到底できない。
次に、実際にタイム中に私が(間抜けにも)ボークを宣告してしまったとして、その時点で「タイム中でした」と取り消しに来てくれれば、対応としては随分違ったものになったはずである。それを、私が走者を三人も進めてしまった後で取り消したのでは、審判員に対する信頼が揺らぎかねない。
失敗は誰にでもあることで、私も多くの失敗を経験しながら審判を続けてきた。試合後のミーティングで、まだ経験の浅いこの球審を責めるような言葉にならないよう気をつけながら、私はよりよい対応をアドバイスし、球審もその言葉を快く容れてくれた。こういった建設的なミーティングを行い、お互いに向上していけるよう反省点を洗い出すことはとても大切なことであり、試合では不手際があったものの、私は晴れやかな気持ちでグラウンドを後にすることができた。
第18回 「『わかりやすい野球のルール』のこと」
私事で恐縮だが、先月中旬に成美堂出版から発行された『わかりやすい野球のルール』という書籍の監修をさせていただいた。非常に大変な面もあったが、とてもやりがいのある楽しい仕事だった。
この本は以前から出版されていたが、今回は全面改定ということで、内容もデザインも一新された。基本的なコンセプトとしては、一般の野球ファンの方にもわかりやすい平易な表現を心がけること、そのために原則として1項目は見開きで完結させること、写真やイラスト等の図版を多用して視覚的な理解も容易にすること等があった。
具体的な作業としては、まず私が公認野球規則の中から最低限必要な項目を選び出し、関連規則はできるだけ近くに配置するなどした項目リストを作成した。結果的に、構成はほぼ原案通りとなった。次に、ライターの方にひとつひとつのルールを私が解説した。総計で10時間近くは喋ったのではないかと思う。
ライターの石川祐一氏は私の話を大変良く理解して下さり、書き上がった原稿には大きな間違いがほとんどなく、とても素晴らしい出来だった。また、取材されている間に石川氏から鋭い質問が発せられることもあり、とても刺激的な時間を過ごすことができた。
ルールの説明をする上で難しいのは、原則論と実際の運用の違いに話が及ぶ場合と、ただ単に複雑なルールの場合である。前者の例としては、ストライクゾーンについての解説が挙げられる。ストライクゾーンはルールでその空間的限界が規定されている。しかし、実際に試合が進行する上では、野球のレベルやそれぞれの組織、審判個々の解釈や技量の違いによってゾーンに違いが出てくることも知っておいてもらいたいと思い、そのニュアンスを含ませられないかと石川氏にお願いした。結果、ストライクゾーンの解説の最後はこのように締めくくられていた。
「とはいえ、プロでも日米で若干の違いがあるように、実際のストライクゾーンは必ずしもこの規定通りではない面もあります。大切なことは、ストライク・ボールは球審が決めるということです。球審には、一定した判定が求められます。」
ストライク、ボールは球審が決めるのだという、ごく当たり前のことが書かれている解説書は今までなかったのではないかと自負している。しかし、石川氏にもっと感謝したいのは、それだけにとどまらず、審判員の技術のことにまで踏み込んで文章を締めくくるうまさである。このことによって、審判がただ絶対者というわけではなく、選手と審判の双方に努力が必要だというニュアンスを含ませられたのではないかと思っている。
このほかにも、野球ルールの原点である「ニッカー・ボッカールール」の精神にも言及していただいたし、野球というスポーツの持つ基本的な考え方や、その歴史的背景をできる限り取り込んでもらったつもりである。その方がルールそのものをシンプルに考えることにもつながると思っている。
また、複雑なルールや文章では分かりにくいルールも、写真を援用したり、具体例を挙げたりすることで便宜を図った。特に投球姿勢については、実際に投球する投手の分解写真や、ボークの場面の写真を利用するなどして表現することを原則とし、言葉だけでは分かりにくい部分が随分補われていると思う。
残念ながら、紙幅の制限があるために最初から解説をあきらめたルールもいくつかあるし、校正の時間が少なかったので、誤植や記述上のミスを見逃してしまったものがいくつもあり、第1刷をご購入いただいた方には申し訳ない部分もある。しかし、アイデアとしては悪くない本に仕上がったと思っているので、増刷以降は細かなミスも全て修正し、よりよい本に仕上げていこうと思っている。
もしご購入いただいた方がいらっしゃれば、是非ご意見やご感想、ミスの指摘等をいただきたい。こういう本は多くの方からの意見が大事だと思っている。
わかりやすい野球のルール@楽天ブックス
第19回 「ストライクゾーン」
最近、大学野球のオープン戦で球審を務めたときのこと。試合開始早々に、先発投手の低めの投球に対して、私が「ボール」と宣告し続けることに捕手が不満を抱いたらしく、何球目かのボール宣告の後で、その捕手は振り返って「低いんですか?」と聞いてきた。私が即座に「低いよ」と返事をすると、捕手は苦笑を浮かべながら首をひねり、その場はそのまま引き下がった。
さらに何人かの打者が打席に入った後、投手は制球に苦しみ(私のせいか?)、満塁のピンチを迎えた。そのとき投手がタイムを要求し、捕手を呼び寄せて何か耳打ちした。次に低めに来た投球を私が「ボール」と宣告すると、捕手は「ミットを持ち上げるからボールにするんですか?」と聞いてきた。私はカチンときて言い返した。「それは関係ない。でも低いと思うから君はミットを持ち上げるんじゃないのか?」
バッテリーがイメージしているストライクゾーンと球審のそれとが一致しないことはよくあることだ。以前にもこのコラムで書いたが、ストライクゾーンはあくまで球審の「解釈」や組織の傾向によって多少は見解のズレが生じるものなので、球審の癖を早く見抜くことが戦術的に重要なことだと思っている。
加えて、一般論として、日本の野球界ではミットをストライクゾーンの方に動かして捕球することや、捕球後にミットを動かすことが「上手なキャッチング」だと思われている。しかし、米国をはじめとして諸外国ではミットを動かすことは「カンニング(ずるい行為)」といって、好ましくない行為とされ、球審はそのような投球に対しては躊躇なく「ボール」を宣告するよう教育されているという。
この試合の捕手も、際どい投球に対しては、ほとんど必ずミットを動かしていた。そのようなことで惑わされることは1試合に数回あるかないかだが、私はミットを動かしたからといって即座にボールにしたりはしない。しかも、その試合では私のストライクゾーンは一定していたし、そのことは試合中に険悪な雰囲気を察した他の塁審から保証してもらった。
なぜ試合開始早々から球審に喧嘩を売るような態度を取るのか私には理解できない。他人からもよく言われるし自分でもそう思うが、確かに私は「低めに辛い」傾向がある。日本のアマチュア野球には内規があり、ストライクゾーンの下限に関してだけ「ボールの全部が通過しなければならない」という取り決めがあるから、それを守ろうとすればどうしても厳しくせざるを得ないのだ。その代わり、といえば語弊があるが、私のゾーンは高めと外に甘い。ストライクゾーンを広めにとって、できるだけ打者が積極的に打ちに行く野球を目指したいと考えているからだ。それを試合の序盤に読み取ってくれれば、楽しい野球ができると思っている。
しかし、多くの選手が審判員に不満を持ち続けるのは、やはりそれぞれが「自分のイメージするゾーン」に固執し、審判員に試合を任せているという意識に乏しいからだろう。以前オリンピックに出場した日本の審判の方が、出場チームの中でミットを動かしたり判定に不服を持って後ろを振り返ったりする捕手は日本以外にはいなかったと語っていたが、多くの人に聞いてもらいたい話だと思う。
結局この試合で、その捕手はふて腐れてしまい、険悪な雰囲気のまま試合を終えた。大変残念なことだが、向こうから喧嘩を売られては仕方がない。それにしても「ミットを持ち上げるからボールにするんですか?」とは、つくづくおかしな質問である。もし「そうだよ」とでも答えれば、彼はそれ以降ミットを動かさなかったのだろうか?
第20回 「おかしな失敗」
今年は変なヘマばかりやらかしている。
たとえば、一塁塁審を務めたある試合でのこと。左打者が思いきり引っ張った痛烈な打球が一塁線を這うように転がってきた。「フェアになるかファウルになるか分からないぞ」と感じた私は、ベースを越える時にどちら側を通過するかだけに神経を集中させて打球を注視した。
打球はベースの外側を通過しそうに見えた。一瞬「ファウルか?」と思ったその直後、驚くべきことに、最後の最後に進路を変えた打球は一塁ベースの「外側」に当たって大きくファウル地域に跳ねた。打球が塁ベースに当たればフェア確定である。頭の中では「あっ、フェアになった!」と判断したのだが、身体はそう反応しなかった。まるでファウル地域に行ったボールを指差すかのように「左手」があがってしまったのである。
これでフェアだと思ってくれる人はどこにもいない。一塁塁審を務めていて、本塁の方を向いたままフェアの宣告をするのなら右手をあげなければならない。それでも瞬時に失敗に反応し、慌てて右手に変えて力強く何度もポイントし、振り返って打球を確認しながらさらにフェアのコールを繰り返して念を押した。取り立ててクレームも何もなかったが、穴があったら入りたくなるような失敗だった。
もうひとつは球審の時のこと。送りバントを試みた打者がバントの構えに入ったところ、踏み出した方の足が完全にホームベースの上に乗るほど、はみ出してしまった。「このまま打ったら完全に反則打球だ」と思いながら投球に注目していたが、外角に外れるボール球にタイミングが合わなかったその打者は、バントの構えのまま空振りしてしまった。この場合、ハーフスイングをとる要領で打者を指差してから、「Yes, he went!(彼は振った)」とコールするのだが、何を考えたのか私は大きな声で「ボール!」とコールしてしまった。
捕手が怪訝そうな顔で、「え、スイングでは?」と振り返ってきたので、慌てて「うん、スイング、スイング」と返事をしてストライクのポーズを作ったが、これも周囲の人から見れば完全な空振りであり、とりたてて問題にはならなかった。
この2つ以外にも、試合の大勢に影響はしないながらも、審判仲間に話せば笑いを取れること間違いなしの失敗をもう少ししているのだが、字数の関係で今回は省略する。いずれにしても、これらの失敗は、以前にこのコラムで書いた「サプライズ」による失敗にほかならない。どちらの失敗も、打球や打者の動きに対して、様々な予測をしていたものの、その予測の範囲外の結果となってしまったことに対して「驚き」が勝ってしまったということだろう。
笑い話で、ストライクと言いかけてボールに変えたために「ストボール」と叫んでしまったとか、握り拳を振りかざしながら「セーフ」と叫んだとかいう話を聞いたことがあるが、私にだっていつそんな日が来るか分からないのだと自分を戒める毎日である。